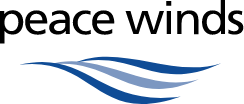【東ティモール】さらなる高品質化と持続的なコーヒー生産に向けた取り組み
ピースウィンズ・ジャパン東ティモール事業では、2017年より助成金をいただき、東ティモール・レテフォホ郡でコーヒーの品質の均一化・高品質化を目指し、コーヒー生産者支援を行ってきましたが、3年目の事業が終了し、一区切りがつきました。
2017年度は従来の収穫の方法や一次加工(コーヒーの実をはずし、発酵させて水洗いの後乾燥させるプロセス)を見直し、品質を管理する能力の向上を、2018年度は完熟したコーヒーチェリーの適切な収穫時期の判別が可能になるよう、完熟したチェリーの色に類似した色のリストバンドを農家に配布しました。また、糖度測定器を導入し、数値で完熟を確認するなどの活動を行ない、それまでは感覚に任せていた作業の適切なタイミングを知った上で収穫が行えるようになりました。また、コーヒーの中に含まれる水分量を適正に保てるように乾燥場を建設し、徹底した水分値・水分活性値管理を行った結果、美味しく飲める期間が各段に長くなりました。


最終年度となる2019年度にはさらなる品質の向上と均一化を目指し、集落内に精製処理施設を建設しました。
精製処理施設とは、コーヒーの皮を外す脱肉機、発酵を行う水槽、乾燥を行うアフリカンベッドというコーヒー乾燥棚が一体となった施設のことです。以前は生産者が各自宅で個別に加工を行っていたため、どうしても品質にばらつきがあり、全体の均一性が課題となっていました。この施設ができたことで、近隣の生産者は収穫したコーヒーを施設に持ち寄り、グループ共通の認識で一次加工を行うことで加工の工程で起こりやすい品質のばらつきを抑えることができるようになり、グループ一丸で品質向上に取り組みました。
また、インドネシア人のコーヒー専門家を2度に渡って東ティモールに招き、初回は施設の設計と加工法を伝授していただきました。 2回目は生産者に対し、良質なコーヒー生産を続けるためには環境保全、特に土壌が肥沃であることが大切であるというテーマで、コーヒーの栽培と土壌改良についてのワークショップを開催してもらいました。良質なコーヒー生産を続けるためには、まず土を豊かにしなければならないと知った生産者は意識が高まり、生産者の多くがワークショップで学んだ土壌改良方法をそれぞれの圃場で実践しました。
広島市での事業報告会
2020年1月に、広島市内のホテルにて事業報告会を行いました。どうして広島?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この事業はひろしま国際センターから助成していただいているため、初の広島での報告会となりました。
当日は東ティモールの概要、生産者の様子、どのような取り組みをし、それによりどのような変化が生れたかを写真や動画などを使って報告しました。今回は、以前より東ティモールピースコーヒーをお使いいただいていた広島県内の自家焙煎店、珈琲屋スプレモさんとMOUNT COFFEEさんのご協力で、東ティモールコーヒーを飲みながらの報告会を開催することができました。
参加者からは、「コーヒーが赤いなんて知らなかった」「コーヒーを買う事でできる国際協力があると知った」「コーヒーがこんなに人の手を経て日本に来ているとはびっくりだ」などの感想をいただき、多くの方が満足したというアンケート結果に、コーヒーの産地や国際協力への関心を高めることができたと実感しました。
私たちも、消費者の皆さまから直接感想や質問をいただくことができ、色々な地域での報告会の重要性に気が付く良い機会となりました。


終わりに
「最近レテフォホでは雨の量が少なくて、雨の降り始めが遅いので地下水が枯れてしまう地域もある。今後はレテフォホのコーヒーがずっと生産できるように森林と水を大事にして、教えてもらった事をきちんと生産者に伝えたい。」本事業に参加したPWJローカルスタッフの言葉です。
また、事業に参加した生産者の一人は「父親からコーヒー圃場を受け継いでコーヒーを生産している。その収入が教育費や医療費、食費になっているので、自分もきちんとコーヒー生産を続けなければならない。PWJの支援で精製処理施設ができて、先生からは新しいことをたくさん教えてもらえた事が良かった。コーヒーの品質がよくなって買い取り価格が上がると嬉しい。コーヒーによる収入を絶やさないためにも教えてもらったことを続けたい」と話してくれました。
これらの言葉から、今回の支援活動を通じて、生産者自身がただコーヒーを生産するのではなく、高品質なコーヒーを持続的に生産するためには環境を保つことが必要であるという事への理解が深まったのは大きな収穫だったと感じます。
今後もPWJは生産者と共にコーヒーを取り巻く環境の配慮を大事にしながら高品質なコーヒーを作り、生産者の収入・生活の向上をはかる活動していきます。
*本事業はひろしま国際センター草の根国際協力助成金事業で実施しました。