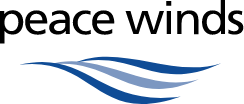【仕事場は地球#01】「申請書に書ききれない“思い”を現場チームと一緒に直接現場を動かして実現していく」――スリランカ代表・川瀬葉子

紛争や災害などで苦しむ人びとを支えるために、ピースウィンズのスタッフは東奔西走しています。その現場は、毎日のニュースに登場する場所もあれば、光の当たりにくい場所もあります。言葉も文化も生活習慣も違う場所で、スタッフたちは何に喜びを見出しながら仕事しているのでしょうか。これから月に1度、困っている人を世界中で支援するピースウィンズのスタッフインタビューをお届けしていきます。第1回はJICA(国際協力機構)青年海外協力隊とピースウィンズ合わせて10年近くスリランカに駐在する川瀬葉子です。
スリランカは“デスティニー”。大変とも、日本に帰りたいとも思ったことはない

―― スリランカとの縁ができたJICAの青年協力隊に応募したきっかけから聞かせてください。
川瀬 海外に興味があったので、日本語の先生になったら海外に行けるかもと考えて大学では日本語教育を専攻したのですが、卒業したときは就職氷河期で思うような仕事が見つかりませんでした。しばらく地元の滋賀と東京で会社勤めをしました。
社会人としてのイロハから、マーケティングや通訳・翻訳、印刷の仕組み、プログラミングなど多くのことを経験して勉強できたのは良かったのですが、2011年に東日本大震災が起きたとき、ふと思ったのです。私はこのままの人生に納得できるのだろうかと。40歳になる少し前でした。
そこでJICAの海外青年協力隊募集を見るようになりました。2013年にスリランカでマーケティングの仕事の募集があったので、これだと思って、第2希望、第3希望は書かずに応募しました。面接で「どうして第1希望のスリランカしか書いてないのですか?」と聞かれて、「デスティニーです」と答えました。
―― “運命のスリランカ”はどうでしたか?
川瀬 本当に大変でした。政権交代があったり省庁再編があったり、予算が決まらなかったり、内戦があった北部のジャフナが任地だったので、いろんなことがあって、政治に巻き込まれた2年間でした。

―― それでも懲りずに帰国翌年の2017年にピースウィンズに入って、スリランカに戻ってきたのですね? どうしてですか?
川瀬 なんと言うか……「手のかかる子ども」みたいな存在で(笑)。たまに改善する様子を見ると、それがうれしくて、またつい世話を焼いてしまうんです。今も腹が立つことも、むかつくこともあるけれど、大変だと思ったことはないし、日本に帰りたいとも思いません。
実際、スリランカはいいところです。駐在しているスリランカ北東部のトリンコマリーは海が近いし、暖かいし、目に入る景色の8割はグリーンで気持ちがいい。もう寒いところでは暮らせません。
一緒に働くローカルスタッフもどんどんいいチームに育っています。ここには課題がたくさんあるけれど、私は隠れた問題を見つけるのが得意で、その問題を何とかして解決するところに醍醐味を覚えています。

―― スリランカでは今どんな事業を行っているのですか?
川瀬 ピースウィンズは2009年からスリランカで人道支援を行ってきていて、当初は内戦後に住民が再定住した地域を中心に、緊急支援や、農業・酪農などの生計を再興する支援を行ってきました。
今は北部州・東部州の再定住エリアを中心に気候変動や経済危機の影響で生活が苦しい人を対象に、化学肥料や農薬に頼らない有機農業の指導をしたり、内戦中に放置されて荒れた貯水池を修繕するといった農業支援を行っています。
さらに、スリランカ北部地域の特殊事情で女性世帯主率が高いので、彼女たちが家計を維持できるよう生計向上支援に加えて、家計簿研修も行っています。
―― どうして夫のいない家庭が多いのですか?
川瀬 内戦の間、結婚すると徴兵されないという暗黙のルールがあったので、徴兵逃れのために偽装結婚する男性がたくさんいました。そういった男性が内戦終結とともにいなくなってしまったのです。子どもを抱えた女性たちの支援が大切です。
自分で構想した支援事業を自分の手で完成させていく

―― Instagramを見ると、通訳を介さずにタミル語やシンハラ語で話しかけて笑いを取るなど、地元に密着して活動している様子が伺えます。日々の仕事のどんなことに喜びを見出していますか?
川瀬 私、スリランカでは何が起こっても何とかできるというヘンな自信があるんです。危機に直面しても、どこかでそれを楽しんでいる自分を発見します。
たとえば、新型コロナが蔓延したとき、スリランカは数ヵ月にわたり2週間ごとに完全なロックダウンになって万事休すだったのですが、特定の業種には「移動許可証」を警察で出してもらえることを大家さんに教えてもらって、警察署長に直談判し、事業を継続することができました。
経済危機でガソリンが手に入らなくなったときは、さまざまな情報を分析して、余剰がありそうなガソリンスタンドを探し当て、私たちの事業の重要性を説明してガソリンを分けてもらいました。
私はスリランカのいいところも悪いところも知っている。それを踏まえて、自分で構想した支援事業を自分の手で完成させていくことが本当におもしろいと思っています。
―― 人道支援をするには国連だったり、JICAだったり、いろんな道があると思いますが、NGOならではのおもしろさとは、どういうことだと思いますか?
川瀬 私たちは支援する相手に近い。だからこそ、こうしたらもっと良くなると思うことを大胆に進めることができる。それがNGOの良さだと思います。
助成金の申請書には自分が考えたプロジェクトを落とし込んでいくわけですが、どうしてもそこに書ききれない思いがある。それを現場に行って、チームと一緒に直接現場を動かして実現していく。それがNGOのおもしろさだと思っています。
たとえば、この地域は雨が降ると洪水になってしまうので、地元の人は「雨期は洪水になるから農業をやらない」と言います。でも、簡単に手に入る籾殻を使って燻炭を作って撒けば水はけが良くなることや、毎日大量に出る枯れ葉を燃やさないで腐葉土にすれば土壌改良ができることなど、ちょっとした暮らしの中の豆知識を伝えることで、人びとの暮らしは目に見えて改善されます。
関西出身のせいか、お節介が大好きなんです。それを発揮できるのがNGOの現場なのかなと思います。
インド洋の島国スリランカはポルトガルやオランダ、イギリスの植民地になった歴史を経て、1948年に独立。80年代にシンハラ人とタミル人の民族対立が激化し内戦となる。2002年、ノルウェーの仲介で政府と反政府組織タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)との間で停戦が成立。その後も各地で衝突は散発したが、2009年、ムライティブの拠点攻撃により政府軍がLTTE実効支配地域をほぼ制圧した。2004年にはスマトラ島沖地震の津波のために沿岸部で3万人が犠牲になった。2020年に新型コロナウイルスが蔓延したあと主要産業である観光業が壊滅し、深刻な経済危機に陥って現在もIMFの支援を受けている。
川瀬 葉子(かわせ ようこ)
大学で日本語教育を学び、卒業後オーストラリアで日本語教師アシスタントをした後、故郷の滋賀で健康食品の輸入代行や美容関連製品の企画販売を行う。その後、東京の医学系出版社や製造業向けITソリューションの会社でマーケティング担当として働く。JICA青年海外協力隊員として2014年から2016年までスリランカ北部のジャフナにマーケティング隊員として駐在。滋賀の会社勤務を経て、2017年ピースウィンズに入職。同年11月から現在までスリランカ代表を務める。