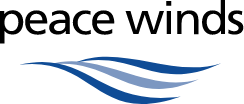【仕事場は地球#04】「諦めないで、もう少し現場を見ていたい。自分で納得できるまで」――ウクライナ・チーム 倉持真弓

世界各地で助けを必要とする人を支援するピースウィンズスタッフは、どんなことを考えながら現場で仕事しているのかを聞く連続インタビュー。第4回に登場するのは、ロシアとの激しい戦争が3年半近く続くウクライナの人々の支援に携わる倉持真弓です。「人を傷つけてはいけないことはみんなわかっているはずなのに、どうして戦争が絶えないのか? 自分なりに納得できる答えを求めて」戦時下の人のそばにいたいと願う倉持の思いを聞きました。
話していると誰かが泣きだすウクライナの現状
―― アメリカに新政権ができてロシアとウクライナの間で停戦が実現するかと希望が生まれたのも束の間、最近また相互に攻撃が激しくなっています。
倉持 去年の秋にも情勢が緊迫しましたが、この数ヶ月また戦闘が激しくなっている気がします。ウクライナにいる現地スタッフと話をしても、「一晩中ドローン攻撃が続いて眠れなかった」というような話をよく聞きます。
―― 倉持さん自身、ウクライナで攻撃を見たり聞いたりすることはありましたか?
倉持 警報が出て地下シェルターに避難したことはありますが、ホテルにいるとドローンの音は聞こえないし、目の前で爆発を見たわけではないので、さほどの切迫感は覚えたことはありません。
ただ、開戦直後に占領された地域の住民の話を聞くと、その時の恐怖が生々しく伝わってきて戦争の実相を感じます。また、誰がどこでどんな支援を必要としているのかを把握するために各地で聞き取り調査をしていると、必ず誰かが泣き出してしまうほど、みなさん不安やストレスで心の負担が限界まで重くなっているのをひしひしと感じます。
とりわけ夫が軍隊に入っていたり戦闘で家族を亡くしたりした女性の悼みを耳にする機会が多いです。こうした苦しみを超えて、戦時下でどう生活していこうかみんな一生懸命考えているけれど、先のことを考えるとそこにまた新たな不安が生まれていることも感じます。
―― どういうことですか?
倉持 ウクライナで必要性が高いと感じている支援のひとつに、将来に希望を持ちにくくなっている若者の心理ケアやキャリアガイダンスなど、居場所と交流の機会を提供する、というのがあります。その準備として、ある市で19歳から20歳の若者の話を聞きました。
彼らは新型コロナウイルスの感染拡大と2022年から続く戦争のために学校の授業がオンライン中心になり、5年以上社会と交わる機会を奪われています。そのために、どうやって人と触れ合えばいいか、どうやって社会に踏み出していくかわからなくて不安だと言います。
将来を考えると海外に出ていく若者が多い一方で、さまざまな理由で地元に留まる人もたくさんいます。兵役年齢の男子は残らざるを得ません。彼らは先のことを考えたいけれど、戦時下では将来設計が立てにくいのが現状です。なので、まずは気軽に集まって交流したり、就労支援を受けたりできる場所を作れないか検討中です。
―― なるほど。若者ならではの深い悩みがあるのですね。ウクライナでは、他にどんな支援が必要だと感じますか?
倉持 東部や南部の前線に近い地域には、たくさんの方が避難所暮らしをしています。特に高齢者や障害のある人にとって避難所生活は不便なことが多いのですが、他に行く場所がないという人が多いので、こうした避難所をもっと住みやすいところにして、さらに理学療法士の指導を得て体を動かす機会を作るなど、健康寿命を延ばすお手伝いをしたいと思っています。ウクライナでは子ども向けの支援に比べて高齢者向けの支援が少ない印象を受けます。ですからそこのギャップを埋めたいと思っています。


―― 東部などの前線はロシアが最近も攻勢を強めていて、地上戦などによってプロジェクトができなくなる恐れはありますか?
倉持 あります。それが戦時下で人道支援を行う難しさのひとつだと思います。以前、別のNGOでカンボジアの教育支援プロジェクトに関わりましたが、内戦が終わって復興に向かっていたカンボジアと、今まさに戦争が進行中のウクライナの大きな違いがこういうところだと思います。

いつか納得のいく答えは得られるのか?
―― 戦時下のプロジェクトは本当に難しいと思いますが、倉持さんがウクライナ支援事業を希望したのはどうしてですか?
倉持 私は知りたいんです。人として「人を傷つけてはいけない」って誰でもわかっていることだと思うのですが、それなのに世界では戦争が絶えない。個人と個人なら傷つけないようにできるのに、集団同士になるとどうして戦争をするのか、それって一体どういうことなのか私はわからないのです。
もちろん、ロシアに攻撃されたウクライナのように、人は叩かれたら痛いし、やり返したいと思う。でも、本当に戦争しか解決方法はないのでしょうか? 地政学的要因、資源の奪い合い、経済格差、民族の違い‥‥戦争にはさまざまな理由があることは頭でわかっていても、私は納得できない。どうしてそうなるのか自分で納得できる答を探したいのです。
人類は共存できるのではないかって、いわゆる「頭の中がお花畑」と揶揄される状態かもしれませんが、私はいまだにそんな希望を持っています。諦めないで、もう少し現場を見ていたい。自分で納得できるまで答えを探し続けると思います。
その模索を続けながら、戦時下の困難な暮らしを続けざるを得ないウクライナの人のためにできることを続けていこうと思っています。
ウクライナ支援事業について
2022年2月24日、ロシアはウクライナに大規模軍事侵攻し一部地域を占領。ピースウィンズはウクライナと隣国モルドバに拠点を置き、危険地域から退避する人たちの支援や避難所への食料・衛生用品・ペット用品の提供、病院への医療機器や医薬品提供などを行ってきた。また戦闘によって破壊された幼稚園の修繕や学校への教育資材提供も実施。戦時下での暮らしが長引くなか、心理社会保護支援などさまざまな活動を行ってきた。
倉持 真弓(くらもち まゆみ)
高校卒業後、渡米。ニューヨーク市立大学ブルックリン校で心理学を専攻。卒業後は、日本で6年、シンガポールで5年、日系企業で広報・IR(投資家向け広報)や、人事などを担当。2020年に日系NGO国境なき子どもたち(KnK)のカンボジア派遣員として、若者への職業訓練や教育支援のプロジェクトに従事。2024年からピースウィンズ職員としてウクライナの隣国モルドバに駐在してウクライナ支援事業に当たっている。
【取材・文】
草生 亜紀子(くさおい あきこ)
The Japan Times記者、新潮社『フォーサイト』副編集長などを経て独立。ピースウィンズ海外事業部の業務を行いつつ、フリーランスで執筆や翻訳をしている。著書に『理想の小学校を探して』『逃げても 逃げてもシェイクスピア』、中川亜紀子名での訳書に『ふたりママの家で』がある。