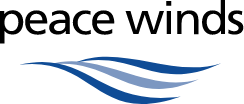【仕事場は地球#05】「手に手を添えるプロジェクト作りを意識している」――ウガンダ代表・井上慶子

世界各地で助けを必要とする人を支援するピースウィンズスタッフは、どんなことを考えながら現場で仕事しているのかを探る連続インタビュー。第5回は世界最大の難民受け入れ国ウガンダに駐在して、「うまくいかない時こそ、イノベーティブに、クリエイティブに考えるチャンス。だから仕事がおもしろくて仕方ない」と語る井上慶子の話を聞きました。
泥臭く働きたいと思った
―― 以前のインタビューを読むと、国連機関で働くことを目指して大学や大学院でインターンなどされていたとか。どうしてNGOで働くことを選んだのですか?
井上 国連機関で実際に働いてみて、自分の価値観とは少し違うと感じたのです。命を救うことに直結する現場で、もっと泥臭く働きたいと思ったのです。そう思った時に、関心のある中東で自分の専門である教育に関係する事業を行なっていたピースウィンズを見つけて、2016年に入職しました。
当時、ピースウィンズはイラクで学校健診を行なっていました。学びの場というだけでなく、子どもの健康診断や大人の心理ケアをする場所として学校を広く有効活用していて、教育と命を救うことの両方に関わる事業に興味を持ったのです。
―― まずはシリアを担当しながら、イラク、ハイチ、モザンビーク事業にも関わり、2021年からウガンダに駐在。南スーダン事業との兼務などを経て、今はウガンダ事業に専念して現地代表なわけですね。「命を救うことと教育の関係」は興味深いので後で改めてお聞きするとして、まずは現在ウガンダで行なっている事業について教えてください。
井上 大きく分けると、ふたつの事業があります。ひとつは農業支援。これまで農家の技術トレーニングを行なってきて、ここからは農作物を加工して付加価値をつけて収益を増やすために、加工施設を作って協同販売のための組合を作ります。
―― 規模の大きなプロジェクトですね。
井上 活動している難民居住地区に住む人たちの7割くらいが農業に従事しているので、ここの基盤を強くしたいと思っています。

――何から、どんな製品を作るのですか?
井上 白とうもろこしを粉末にしたものをお湯で練ったポショをみんなよく食べるので、この粉を作ります。また、豆を挽いてペーストにしたものにも高い付加価値がつきます。こうした製品にいずれ国の認定を受けて、難民居住地の名前をつけて「チャカブランド」として売り出したいです。
――もうひとつは?
井上 女性と若者のエンパワーメントを行なっています。これはUN Women(国連女性機関)の事業で、ピースウィンズがリーダーとして、ウガンダのNGOやJICA(国際協力機構)、トヨタ・ウガンダ、ウガンダ発のアフリカンプリントのバッグなどを製造販売する民間企業RICCI EVERYDAYなどと提携して、女性農家の稲作支援や縫製などの職業訓練、自動車修理技術の訓練、ITトレーニングなどさまざまな活動を行なっています。
コンゴ民主共和国からの難民が多いチャカIIとナチバレ、南スーダンからの難民が多いアジュマニ、ユンべ、ライノキャンプの5つの難民居住地区で、地区ごとにさまざまな活動をしています。

――ウガンダでは難民キャンプという言い方をしないのですよね。
井上 難民キャンプではなく難民居住地区と呼んで、難民の人たちが出入り自由で、教育や医療サービスにアクセスできるようにして、就職したり起業したりできるよう難民の自立を促しています。生活の基盤がウガンダにできた人も多く、10年とか20年とか長く暮らしている人もいます。
教育が命をつないでくれた
――少し話を戻します。最初に「教育と命を救うことの両方に関わる事業に興味を持った」と言われました。詳しく聞いてもいいですか?
井上 これは私自身の経験からきています。学生の時、病気になって命の危機に瀕するまでになりました。入院して治療しなければいけないレベルだったのですが、私は勉強が大好きで、どうしても勉強を続けたかったのです。その時、理解のある女性医師に出会うことができて、大学と治療を両立させる道を一緒に模索してもらうことができました。
「専門知識を身につけて、海外で困っている人に手を添えて乗り越えた明日を一緒に見たい。一緒に生きていきたい」という夢を叶えるために、どうしても学業を続けたかった。大学では公衆衛生を専門とする先生が、体調が万全でなくてもシリアでの実習に参加させてくれ、大学院では国連機関インターンの機会を得るなど、多くの人に支えてもらいました。学業を続けるという希望が生きる活力になり、私の場合、本当の命綱になりました。この経験から、教育は命に直結すると思っているのです。
――信念を持って仕事している様子が伝わってきますが、習慣も文化も違うアフリカでの仕事は、思い通りにいかなかったり辛いことはないですか?
井上 私は現地スタッフに「アフリカ人っぽい」と言われることがあります。うまくいかないことは確かにあるのですが、そういう時ほどおもしろいと思っていて、どうやって乗り越えるかを考えるのが好きです。そういう時こそイノベーティブでクリエイティブに考えるチャンス、自分たちや人びとが成長できるチャンスだと思うから。
現地スタッフと議論すると、一緒にいろんなアイディアを出してくれます。現地スタッフのみんなは本当に頼りになる人たちで、ハッとするようなたくさんの気づきと刺激をもらっています。たまに意見が食い違うことはありますが、一日中ご飯も食べないで議論して、最後は泣いて笑って分かり合えたこともありました。言葉や文化が違っても人間は同じだし、何があっても「人間らしくていいなあ」と、おもしろがっています。苦楽を共にしている実感があります。

――仕事の喜びを感じるのは、どういう時ですか?
井上 人道支援はともすると支援する人が偉い、みたいなことになりがちですが、私はそうではなくて、事業は一緒にやるものだと思っています。支援を受ける人と対話を重ねながら事業形成する。彼らの手に手を添えるようなプロジェクト作りをいつも意識しています。手を添えることで彼らのポテンシャルを引き出して、生活を変えていく。それができた時に醍醐味を感じます。人びとと一緒に可能性を広げ、未来を作る。そんな仕事はすごく楽しいですよ!
ウガンダ共和国はケニア、タンザニア、ルワンダ、コンゴ民主共和国、南スーダンに囲まれた内陸国。1962年にイギリスから独立。1970年代は、イディ・アミンの恐怖政治で混乱をきたした。1981年から86年までの内戦を経て政権を握ったヨウェリ・ムセベニは、39年間大統領の座にある。現在は周辺国から170万人以上の難民が流入し、世界最大の難民受け入れ国となっている。
井上慶子(いのうえけいこ)
神奈川県生まれ。神戸大学大学院博士課程後期修了(PhD)。専門は教育経済、教育社会学など。大学および大学院在学中に、FAO日本事務所、ウガンダ教育スポーツ省、UNESCO統計研究所アジア太平洋地域事務所、FHI360(米国NGO)、UNICEFジンバブエ事務所などでインターン。2016年9月にピースウィンズに入職。シリア事業従事の傍ら、イラク、ハイチ、モザンビーク事業などにも携わる。2021年10月より、ウガンダ駐在。南スーダン事業とウガンダ事業の兼任、南スーダン事業専属を経て、現在はウガンダ現地代表。
【取材・文】
草生 亜紀子(くさおい あきこ)
The Japan Times記者、新潮社『フォーサイト』副編集長などを経て独立。ピースウィンズ海外事業部の業務を行いつつ、フリーランスで執筆や翻訳をしている。著書に『理想の小学校を探して』『逃げても 逃げてもシェイクスピア』、中川亜紀子名での訳書に『ふたりママの家で』がある。