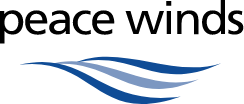TICAD9イベント「映像が伝える難民支援の最前線」ご報告 ケニアから見る難民支援の未来

横浜市で8月20日から22日まで開催された「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)」で、ピースウィンズはテーマ別イベント「映像が伝えるケニアの難民支援の最前線」を主催しました。約50名の来場者を前に、ピースウィンズのカメラマンが捉えたケニア北西部に位置するカクマ難民キャンプの取材映像をもとに、ピースウィンズのこれまでの難民支援の取り組みを振り返るとともに、ケニアにおける難民支援が現在直面している課題について議論を深めました。
企業や国際機関など関係者の皆さまをゲストに迎えたことで、ピースウィンズが支援時に重要視しているマルチセクターとの連携を体現するイベントとなりました。以下、その内容をご報告します。
長期化する難民支援が抱える課題、現地からのレポート
紛争や迫害などをきっかけに命の危機にさらされ、母国を追われた「難民」。彼らが避難先で一時的に暮らすのが、難民キャンプと言われる場所です。
ケニアの難民キャンプはソマリアや南スーダンやコンゴ民主共和国など、さまざまな国の難民が暮らしており、その設立は30年以上前にまでさかのぼります。設立後から流入は止まらず、現在ケニアには約85万人の難民・庇護申請者がいると言われています。

イベントの序盤では、海外の支援の現場から生の情報を伝えてきたピースウィンズのカメラマン、近藤史門、ケニア事業を担当する海外事業部の大門碧が登壇し、動画で現場の様子を紹介しながら、難民支援が抱える問題を伝えました。
▼近藤が撮影したケニアの難民キャンプの映像は、ピースウィンズ公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます▼
焦点となったのは、難民の自立支援です。これまでのキャンプ収容政策により、難民キャンプにやってきた人々は、基本的に自由な移動や就労ができないため、国際機関やNGOなどの支援に頼って生活せざるを得ない状況に陥ってきました。しかし、受け取った援助でただ生きていく以外の選択肢がない状態では、支援の持続性が危ぶまれるだけではなく、難民自身の生きる活力を奪ってしまう──。そんな問題意識から「自分で自分の未来のために活動できる環境の整備」を提言しました。

衛生支援の事例も取り上げました。ピースウィンズはケニアで、難民自身やホストコミュニティの住民たちを活動の主役に据えた、コミュニティを主体とする衛生支援プログラムを実施してきました。
大きな成果を上げたプログラムの1つが「トイレ」に関わる支援です。人が集まって暮らす土地で衛生的なトイレが不足していると、衛生環境の悪化に直結します。事業開始当時、現地では屋外排泄が常態化してコレラ等の感染症が頻繁に蔓延し、人々の健康に大きな影響を与えていました。
しかし、これまでトイレを使用する習慣がなかった人たちに一方的にトイレを提供するだけだった頃は、人々にとってトイレはどうでもよいもので、家計の足しにするために建設資材を売ってしまうということもよくありました。また、約5家族が一つのトイレを共用していましたが、ほとんどのトイレは清掃されていないため、誰も入りたくないような状態でした。
そこで、自分の地区における屋外排泄の実態、健康や家計への影響を、人々が直視し、自分ごととして捉えられるように参加型の様々な活動をおこない、かれら自身が屋外排泄廃絶の行動計画を作成し、実施することを支援しました。この結果、人びとが衛生環境の維持、改善は自分たちの責任であることを認識し、そのための行動(トイレの建設、適切な利用と清掃、手洗い施設の設置など)をとるようになり、さらには屋外排泄がなくなり清潔になったコミュニティを誇らしく思うようになりました。
この衛生支援が展開された難民が住む対象地域では、2021年に屋外排泄ゼロを宣言できるまでになり、こうした結果を受けて本事業はケニア政府から、強制移住の影響を受けたコミュニティにおける衛生改善の好事例としても選ばれました。
▼ケニアのトイレ事情についてはこちらの動画をご覧ください▼
本イベントでは、この衛生事業に協働パートナーとして関わった事例を企業の目線からも紹介いただきました。株式会社LIXILの坂田優氏に、衛生課題の解決のために設置しやすく低価格な簡易トイレ「SATO Pan」を開発した取り組みについてお話しいただきました。

ケニアでも使用されたこのトイレの実機は会場にも用意され、来場者は実際にシンプルに見えながらも創意工夫がつまったSato Pan機を手に取りながら、LIXIL社の現場に向き合った取り組みを実感していました。

▼ケニアでの取り組みについてはこちらの記事もご参照ください▼
【仕事場は地球#02】「誰もが尊厳を保ち、生きがいをもって生きていくことを後押していきたい」――ケニア代表・千葉暁子
「隔離ではなく統合」で描く難民支援の未来
難民支援の課題である難民問題の長期化に伴う援助の長期化、恒常化。この問題の解決を目指して、難民の側に変化を起こすアプローチが自立支援だとすれば、受け入れ社会側のシステムの見直しも進んでいます。
スペシャルスピーカーとして登場した、国連人間居住計画(UN-Habitat)のEric Muchunku氏は、ケニアで進められてきた「統合定住地」構築について紹介し、そこで一緒に働くUN-Habitat、ピースウィンズをはじめ各アクターの貢献を語りました。それまでの政策下の「難民キャンプ」では、難民は決められた敷地の中で支援を享受しながら生きるしかありませんでした。

そこからさらに、難民をケニアの現地社会に取り込み、統合的に開発を進めようというのが「統合定住地」の考え方です。権利が制限されていた難民にも行政・金融サービスなどを開放して経済的な自立支援を促し、さらに現地社会の発展にも繋げる、そんな好循環が期待されています。ケニア政府はこの考え方に基づいて、難民の社会統合を目指す「難民統合計画(シリカ・プラン)」を策定しています。
もっとも、難民の継続的な流入や国際支援の予算不足など、この新たな試みにも多くの課題が立ちはだかっていると、Muchunku氏は指摘しました。ピースウィンズからも国際的な支援が急激に減少するなかで、難民の人びとが支援体制の変化に大きな不安を抱えていることを共有しました。
企業などの民間セクター、人道支援機関である国連機関やNGO、そして受け入れ国の行政の力を結集させることが、これからの難民支援の鍵となる──。そんな多様な連携と複合的なアプローチの重要性を共有し、セッションは終了しました。
最後に設けられた質疑応答の時間には、来場者からの質問が相次ぎました。現地のトイレ事情やSATO Pan機導入に関する疑問が複数寄せられたほか、現場で活動する職員に向けて「本で勉強することと、実際に現地に行って知ることの違いは?」といった質問も出ました。イベントの終了後も登壇者への個別の質問が絶えず、ケニアの難民支援への強い関心を生み出すイベントとなりました。

国際的な支援が先細るなか、現地が自立できる道筋を支える持続可能な難民支援はこれまで以上に重要になっています。ピースウィンズはケニアを始め、各地で難民支援に取り組んでいます。共に課題解決に取り組むパートナーの皆さま、そして支援者の皆さまと一緒に、これからも難民の人々の希望を灯す道を模索していきます。