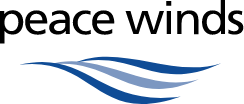【仕事場は地球#07】「夢はアヒルの村をつくること」――モザンビーク現地事業責任者・岩野奈緒

世界各地で助けを必要とする人を支援するピースウィンズスタッフは、どんなことを考えながら現場で仕事しているのかを探る連続インタビュー。第6回は、大学時代に浮遊生物を研究して「私も浮遊生物。人生さまよっています」と笑うモザンビーク現地事業責任者・岩野奈緒の話を聞きました。
専門は浮遊生物学
――略歴を見て、ちょっと意外だったのですが、東京海洋大学海洋科学部出身なんですね。どうして海洋大学だったのですか?
岩野:国立大学で、関東で比較的入りやすい大学だったのが理由のひとつですが、海のそばで育って、サーフィンをする父に連れられて小さい頃からボディボードをやっていたので、海を身近に感じていたのがもうひとつの理由です。
――大学はどんなところでしたか?
岩野:入ってびっくりしたんですけど、専門性の高い大学なので、みんな「好きな海洋生物」とかいてマニアックなんです。水族館めぐりやダイビングが好きだったり、船舶免許持っていたり。私はそこまで魚が好きなわけじゃなくて、失敗したなと思いました(笑)。
――最終的には何を専門にしたんですか?
岩野:浮遊生物学。自分で泳げなくて、海に浮かぶプランクトンとかです。バラスト水ってわかりますか?
たとえば、タンカーがサウジアラビアから原油を運んでくると、帰りは船が空っぽになるとバランスが悪くなるので、水を積んでいきます。帰った港でそれをそのまま放出すると外来生物を持ち込んで生態系を壊してしまう。それを防ぐために、放出前にバラスト水を処理しましょうというのが、その頃、海の法律として定められました。
なので、バラスト水の中の浮遊生物を殺すために化学薬品、放射線、遠心分離といった方法を企業と協力して研究していました。私は、放射線を使った研究でした。

――へえー! それが巡り巡って人道支援にたどり着くまでを聞いていきます。在学中にトルコのイスタンブール大学に留学したんですね。
岩野:国際交流サークルに入っていて、トルコ関係の行事があって手伝いに行ったら、留学生を募集中と聞いて応募しました。留学費用に加えて生活費も支給される好条件で。
――トルコ語はできたんですか?
岩野:まったくできなくて苦労しました。授業は英語で受けられるという触れ込みだったのに、行ってみたら全部トルコ語でまったくわからない。それで半年くらい午前中はトルコ語のコースに入って、トルコ人と共同生活する寮生活を送って、グーグル翻訳を駆使しながら、なんとかしましたが、「こんなにできない日本人は初めてだ」とかガチで怒られて、追試に追われて、本当に大変でした。
後からわかったのは、私より前の日本人留学生はみんな真面目で優秀な院生だったようです。私は勉強がすごく嫌いなんですけど、この時ばかりは図書館にこもって一生懸命勉強しました。
自分でプロジェクトをいちから立ち上げたい
――浮遊生物を勉強していた岩野さんが、人道支援に関心を持ったのはどうしてですか?
岩野:トルコ留学中にシリア紛争が起きて、一時帰国していたシリア人の友達がトルコに戻って来られなくなったり、毎日の通学路がある日、段ボールで寝ているシリア難民で溢れかえる光景を見たりして、「自分にできることは何かないのだろうか」と思い始めたのが、きっかけのひとつです。
もうひとつは、ロカンタと呼ばれるイスタンブールの大衆食堂で食事していると、国際協力を行う日本の建設会社の人がいて、トルコの地下鉄や橋を造っているのを見聞きしました。日本人として誇りに思いました。
その後、イギリスのリーズ大学大学院に進んで、持続可能性のある環境と開発を学びました。水産のバックグラウンドを活かして、小規模養殖を通した生計活動や栄養改善とか研究していました。
――それで帰国後、JICAのインターンをするわけですね。
岩野:JICAの面接に落ちたんです。面接に行ったら他の人はみんな本当にしっかりしていて圧倒されました。私は浮遊生物なので、人生「どうにかなる」くらいにしか考えてない(笑)。それでインターンに応募しました。
――なぜ、モザンビークだったんですか?
岩野:水産分野の募集があったのが、カリブ海とモザンビークだったから。事業を提案できるモザンビークに応募しました。
――その後、開発コンサルティングの会社を経て、2019年にピースウィンズに入るわけですが、どうしてNGOに移ったのですか?
岩野:海外の開発コンサルティングもやっている会社で、居心地のいいところだったのですが、基本的に枠組みがすでにできているプロジェクトの細部を提案する形だったので、自分でプロジェクトをいちから立ち上げたいと思ったのがNGOに転職した理由です。
最初、ミャンマーの駐在員候補として採用されたのですが、本部で仕事している間にモザンビークでサイクロンの被害があって、「何かできないですか?」と言ったら、「自分でやりなさい」みたいなことになって、ミャンマーに行くより前にモザンビークに行くことになりました。
――モザンビークに縁があったのですね。
岩野:そうですかね。その後、ミャンマーにも行ったのですが、新型コロナウイルスの蔓延があって、続いてクーデターがあって、結局ミャンマーには戻れなくなって、モザンビークに戻りました。

――そして2023年2月にトルコ・シリア大地震が起きて、トルコに戻ることになったのですね。
岩野:この頃はモザンビークの事業をやりながらトルコ事業もする兼務状態で、しばらく大変でした。でも、トルコの人びとのためにできることはやりたいという気持ちでした。トルコは親日的で、過剰なまでのおせっかいを焼く人がいたりして、大好きな国です。今もトルコのためにできることはないのか考え続けています。
将来につながるプロジェクトを増やしていきたい

――今はモザンビークの責任者として、モザンビークに専念しているのですよね。モザンビークでは、どんな事業を行っているのですか?
岩野:去年12月にサイクロンで大きな被害が出て、その緊急支援を行っていました。加えて、今年7月末に北部カーボデルガード州でまたも武装勢力による攻撃が発生して、新たに約5万人の国内避難民が発生しているために、こちらの緊急対応にも追われています(*)。
屋外で避難生活を送る人びとのためにピースウィンズはUNICEFの資金でトイレを建設し、トラックでの給水支援と衛生啓発活動を行うことにしました。でも緊急事態の連続でスタッフたちも疲れていて、時々「同じことの繰り返しをしているんじゃないか」と途方に暮れることもあります。
*)【関連記事】北部カーボデルガード州シウレ郡で再び国内避難民の発生
――緊急事態が続く中で、中長期的なプロジェクトを進めるのは難しいことでしょうね。
岩野:プロジェクトをやった後のフォローアップが十分にできていないことが、もったいないと思っています。なので、少しずつですが、農業支援で種や肥料を配って終わるのではなくて、買い付けをする人と手を組んでビジネスにつなげていくとか、将来につながるプロジェクトを増やしていきたいと思っています。
今、やりたいと思っているのが、アヒルの村をつくること。ある村で、増やせるようにつがいのアヒルを配りました。しばらくしてから、「きっと今頃はアヒルが増えているだろうな」と楽しみに行ってみたら、病気で死ぬか食べちゃうかして、アヒルが残っていない。
今日食べちゃうより、育てて増やして売れば将来の収入が増えることを伝えていたのですが、実際は日々食べるものに困っている状況のため、なかなかわかってもらえない。今年はもう少しこれに力を入れてみたいと思っています。
夢は、アヒルの村です。
モザンビークについて
独立は1975年6月。1989年に社会主義体制を放棄。北部を除いて1992年に内戦は概ね終結したが、最北部ではイスラム系武装勢力によるテロ活動で民間人が標的にされ、2021年には70万人以上が避難する事態となった。2025年夏、武装勢力による放火や暴行が起き、新たに約5万人の国内避難民が発生した。毎年のように大規模な熱帯低気圧やサイクロンが上陸し、多くの人が被害にあっていることもあり、貧困に喘ぐ人が多い。識字率60%、2018年の平均寿命は60.2歳で世界平均より12年短い。
モザンビーク事業について
ピースウィンズは、2019年に最大級のサイクロンが南部アフリカを襲った際に150万人が被災したモザンビークで緊急人道支援を開始。2021年以降、北部から紛争を逃れてきた人びとへの支援も開始。特に力を入れてきたのが給水と衛生活動。各地に60基の井戸など給水施設を建設・修繕し、安全な水を確保した。農業をするための種子や道具の配付と技術支援も行って、作物を販売して収入を得られるようにした。
岩野 奈緒(いわの なお)
東京海洋大学海洋科学部卒業。在学中にトルコのイスタンブール大学水産学部に1年半交換留学。英国リーズ大学院より修士号取得。JICAモザンビーク事務所インターン、中央開発株式会社を経て、2019年ピースウィンズ・ジャパンに入り、モザンビーク事業、ミャンマー事業、モルドバ事業、トルコ事業との兼任を経て現職