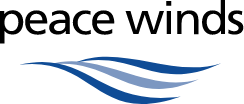【解説】ロシアとウクライナ、今後どうなる? 3年ぶり直接交渉も遠い停戦

ロシアとウクライナの停戦交渉がトルコ・イスタンブールで5月16日に行われました。両国の対面での協議が実現するのは、ロシアが軍事侵攻を始めた直後の2022年3月以来となります。しかし、ロシアが強硬な姿勢を堅持するなか解決の糸口は見えず、交渉の難航が浮き彫りになる結果となりました。双方が望んでいるはずの「停戦合意」がこれほど難しいのはなぜなのでしょうか? ウクライナ戦争の基本知識や前提を抑えておきましょう。
※2025年8月、ロシア・ウクライナ戦争の停戦を巡ってアメリカを仲介役とした交渉が活発化しています。その最新情報をこちらの記事で解説しています。
▶【解説】ロシア・ウクライナ戦争は終結に向かうのか?アメリカが仲介する停戦協議の行方
2月:ウクライナで親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚(マイダン革命)。
3月:ロシアがクリミア半島を併合(国際的には違法とされる)。
4月以降:ウクライナ東部ドンバス地域(ドネツク・ルハンシク)で親ロ派武装勢力とウクライナ軍との戦闘が始まる。
■ 2015年:ミンスク合意(停戦合意)締結
2月:ドイツとフランスの仲介で「ミンスク2合意」が成立。しかし、停戦は断続的に破られ、根本的な解決には至らなかった。
■ 2021年:ロシアの軍備増強と緊張の高まり
ロシアがウクライナ国境付近に10万人以上の兵力を集結させ、NATOとの緊張が激化。
ウクライナのNATO加盟志向や西側との接近に対するロシアの反発が強まる。
■ 2022年2月:全面侵攻の開始
2月21日:ロシアがドネツク・ルハンシク両地域の「独立」を承認。
2月24日:露プーチン大統領が「特別軍事作戦」としてウクライナ全土への侵攻を開始。
首都キーウなどが攻撃対象となり、多くの民間人が被害を受ける。
■ 2022年〜2023年:戦況の推移と反転攻勢
2022年3月:ロシア軍がキーウ周辺から撤退(戦略変更)。
2022年9月:ウクライナ軍がハルキウ州を奪還するなど反転攻勢。
2022年10月:クリミア橋爆破事件が発生、ロシアが報復としてインフラへのミサイル攻撃を強化。
2023年春~秋:ウクライナが南部(ザポリージャ・ヘルソン)方面で反攻作戦を展開。
■ 2024年〜2025年:戦局の膠着と外交的動き
2024年:戦局はほぼ膠着状態に入り、塹壕戦が続く。
2025年3月〜5月:米国やトルコが仲介する停戦交渉が再開。
ゼレンスキー大統領は停戦に前向きな姿勢を見せるが、ロシア側は慎重姿勢を継続。
ロシア・ウクライナ戦争の現在の状況は?

5月16日、3年ぶりに行われたロシアとウクライナの直接交渉は、本格的な進展はなく終了しました。双方が各1000人の捕虜交換や協議の継続で合意するなど対話姿勢は演出したものの、肝心の停戦に向けての協議については、主張に根本的な隔たりがあることが改めて明白になりました。
ウクライナ側は、ロシアの要求について「実現不可能」と述べたと伝わっています。もともとロシアのプーチン大統領がこの交渉への出席を見送り、両国の首脳を欠く代表団同士の協議となったことで、大きな進展は見込めないとの予想も増えていました。
さらに5月18日、ロシアはウクライナに対し、戦争開始以来、最大規模となるドローン攻撃を展開。ウクライナ側はこの攻撃で1人が死亡、3人が負傷したと伝えています。和平交渉終了直後の大規模攻撃は、両国の停戦への険しい道のりを示すものになりました。
そんななか、トランプ大統領は5月19日にロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談に臨むとしています。トランプ氏の仲介の行方が注目されますが、両者の立場の乖離は大きく、停戦に向けた具体的な進展にこぎつけるのは容易ではないとみられています。
ロシア・ウクライナ戦争はなぜ起きたのか?

ウクライナ戦争が「泥沼化」した経緯について、振り返ってみましょう。
発端は2022年2月24日、ロシアのプーチン大統領が「特別軍事作戦」を宣言し、ウクライナ全土に侵攻を開始したことでした。ウクライナの各地の都市にミサイルが撃ち込まれ、ロシア軍は複数のルートで進撃、政権転覆を狙ってウクライナの首都キーウに迫ります。
しかし、空港の制圧に失敗するなど首都近郊でウクライナ軍の激しい反撃に遭ったことで、ロシア軍は首都制圧を断念。キーウ周辺から撤退し、戦線を東部や南部に移しました。
ロシアの軍事侵攻を欧米諸国は強く非難し、経済制裁を段階的に実施することになります。また西側諸国から兵器の支援を受けたウクライナは反転攻勢を強め、「ハルキウ反抗」などでロシアに占領された土地を奪還するなどの戦果を上げました。

その後も両者の攻撃は続き、戦争は3年以上にわたって続いています。この戦争の過程で戦場となった、あるいはミサイルによる空爆が行われたウクライナの各地で、多くの民間人が犠牲になりました。特にキーウ近郊の都市ブチャで明らかになったロシア軍による住民の虐殺は、ウクライナ戦争の悲惨さ、残酷さを示す象徴的な事件となりました。周辺諸国に脱出し難民となった人も数百万人に上りました。
侵攻直後の2022年3月には、ロシア・ウクライナの両国が停戦を模索し、トルコのイスタンブールで和平交渉が行われたことがありました。しかし、一部の項目で妥協点が見いだせなかったことや、ブチャの虐殺事件が明るみに出たことで交渉は決裂。それ以降、本格的な和平交渉は長らく行われてきませんでした。
当初の予想や戦力差を覆してロシアに対抗してきたウクライナですが、戦争が長期化するなか、持久戦に分のあるロシアが優勢となる場面も増えています。こうした状況からロシアが自身の立場を譲らず、強気に協議に臨んでいることも交渉が進まない原因のひとつとなっています。
ロシアとウクライナの歴史的な関係

ロシアとウクライナは、どちらもスラヴ国家のキエフ公国が源流とされています。民族的にも近しいとされる両国ですが、その歴史は支配と対立の繰り返しでした。
1922~1991年の旧ソ連支配の時代、ウクライナはソ連の一部となりました。スターリン時代にはウクライナ語の弾圧など文化的な抑圧のほか、過剰に食料を徴収されたことで人為的な大飢饉「ホロドモール」も発生し、多くの人が犠牲になりました。ソ連崩壊後、ウクライナは念願の独立を果たしますが、ロシアの影響力は根強く残っています。
現在につながるロシアとウクライナの対立を決定的にしたのが、2014年に起こったロシアによるクリミア半島の併合です。クリミアはウクライナ領ですが、ロシア語を話す人が多いなどロシア寄りの文化圏で、黒海に位置する戦略的な要衝でもあります。
ウクライナで親露派の政権が崩壊し、親欧米派政権が樹立されたことがロシアが動き出すきっかけになりました。一方的な併合後にロシア主導の「住民投票」を実施し、その結果を根拠にロシアへの編入を宣言。この住民投票は国連決議で無効とされましたが、ロシアは事実上クリミアを今も支配し続けています。

ロシアがウクライナへの警戒心を強めた背景には、ウクライナがNATO(北大西洋条約機構)加盟を志向していることもあるとみられます。ウクライナは2002年、NATO加盟の意向を正式に表明し、2008年にはNATO側がウクライナの将来的な加盟を明記しました。ロシアは、隣国ウクライナのNATO加盟を国家安全保障への脅威として強く反発しており、クリミア併合、そして軍事侵攻の一因となった可能性があります。
一方でロシアのこうした行動が、ウクライナにNATO加盟の必要性をより強く認識させることにもなりました。
紛争はいつ終わるのか?和平交渉が難航する理由

3年以上にわたる戦争はウクライナ、ロシア双方に甚大な被害をもたらし、多くの人々から平穏な日常を奪っています。この悲劇を一刻も早く終わらせるため、国際社会が仲介しての和平交渉の動きが加速しています。しかし、ロシアとウクライナの主張に隔たりがあることから、合意までの道のりは長いとみられています。
ロシアは合意の条件として、実効支配地域の保持、つまりこの戦争で占領したウクライナの土地をロシア領として承認することなどを主張しています。この要求を聞き入れることは、今回の戦争で繰り広げられた武力による現状変更や主権侵害を追認するに等しく、ウクライナだけでなく国際社会にとっても受け入れがたいことです。
またロシアはウクライナの「中立化」、つまり西側諸国の影響力を排除することを求めています。具体的には、ウクライナが今後永久にNATOに加盟しないという法的保証や、軍事的な連携の禁止、ウクライナ軍の軍備抑制などを指します。「中立化」と表現しているものの、ウクライナを再びロシアの影響下に置く目的があることが明らかなため、この要求に対してもウクライナは強く反発しています。

ロシアは現状、前線での戦闘を優位に進めているという立場で協議に臨んでいます。このため和平交渉に応じる姿勢こそ見せるものの、本質的な妥協には消極的で、自身の主張を取り下げる気配はありません。一方で、ウクライナ側もロシアの要求を呑むわけにはいかないという立場です。
19日には、両国の仲介に意欲を見せるトランプ米大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談を行い、停戦に向けた交渉の進展が期待されましたが、即時停戦に応じることはなかったといいます。
平和的解決を望みながらもロシア、ウクライナ両国の「譲れない一線」がぶつかり合い、停戦の実現はいまだ見通しが立たない状況です。
【現場からの報告】「生きていることが辛い」長期化する戦時下のウクライナの人びとに寄り添う支援を

戦争が3年以上も続いているウクライナでは、 攻撃による直接的な被害に加えて、住居や健康、メンタルヘルス(心の健康)に関連した問題が顕在化しています。
ロシア軍による占領や爆撃によって住む場所を追われた人びとは、快適な環境とは言えない避難所で不便な暮らしを続けています。そのなかでも特に足が不自由なお年寄りや障害者の方たちは「帰る家もなく、かといって自分で住居を探して生活していくのは難しい。避難所で一生を終える」と話してくれました。1日中避難所の部屋の中で過ごしていると運動量も減り、健康を害する人も少なくありません。

また、訪問した高校の先生によると、戦争の終わりが見えないなかで将来の展望が描けなくなっている若者が増えているようです。未来の希望を失った若者が自暴自棄になるリスクも高まっているため、精神的な支えが必要になっています。
ピースウィンズはこれまで、保健医療支援や建物の修繕、生活物資配付などの活動を行っており、現在も被災者に寄り添い支援を続けています。中高生を対象とした心のケアとして実施しているグループセラピーでは、参加した生徒から「自分が抱える不安にどう対処すればよいかわかった」「不安なときにどのように呼吸すればよいかわかった」という感想が寄せられている一方で、「生きていることが辛い」といった相談が持ち込まれることもあります。
私たちは、長期化する戦時下のウクライナに生活する人びとが直面している問題に対し、今後も支援活動を続けてまいります。