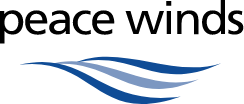【仕事場は地球#02】「誰もが尊厳を保ち、生きがいをもって生きていくことを後押していきたい」――ケニア代表・千葉暁子

世界各地で助けを必要とする人を支援するピースウィンズスタッフは、どんなことを考えながら現場で仕事しているのかを聞く連続インタビュー。第2回は、JICA(国際協力機構)の調整員や専門家、ピースウィンズ合わせて13年近くケニアで活動する千葉暁子の話を聞きました。経歴を見ると支援一筋のようですが、当人は「行き当たりばったり」の人生を歩んできたと言います。どういうことなのでしょう?
関心を持つきっかけはエチオピアの飢餓
――人道支援の仕事に興味を持ったきっかけは何でしたか?
千葉:小学生の頃、当時UNICEFの親善大使をしていた黒柳徹子さんをテレビで見たのがきっかけでした。黒柳さんがエチオピアの飢餓の話をしていて、日本には古いお米が余っているというのに、どうして飢える人がいるのか、何とかできないのか、何かしたいという気持ちになったことを覚えています。
ただ大学を出る頃には、「自分は人を助けるような立場の人間か?」とかあれこれ考えてしまって、企業への就職を選びました。でも、やっぱり違うと思い直して、日本語教師の資格を取って青年海外協力隊に応募し、24歳の時にエジプトに派遣されました。これがすごく楽しかったのです。
――それで人道支援の道に?
千葉:いいえ。大学の時に指導を受けた文化人類学者の大塚和夫先生がアラブ研究の第一人者だったこともあり、母校の大学院に進んで引き続き指導を受けることにしました。でも修士課程の途中で結婚したり、JICAのプログラムでフィールド調整員を探していると声をかけられたこともあって、2006年に大学院を休学してケニアに来ることになりました(一年後に夫も合流)。

当時ケニアでは、ビクトリア湖周辺地域のHIV感染率が20%を超えるなど大変な状況でした。大学院で研究していたセクシュアリティやリプロダクティブヘルスの問題とも密接に絡んでいたので、多くを学ぶことができました。この時に、ケニアの官庁やJICA、地元の人などさまざまな機関や人の間を調整して、予防啓発活動などをするおもしろさを知りました。
この仕事を3年やっているうちに、当時JICA企画調査員としてケニア事務所にいた小児科医の公文和子さん(その後、ケニアの障害児とその家族を支援する「シロアムの園」を設立)に声をかけていただいて、JICAの個別専門家として地域保健プログラムの改善に関わることになりました。
コミュニティの人たちや地方の保健局の人たちと一緒にプログラムを実施して、その学びを中央政府に共有して改善を提案し、それをまた地元の人たちと一緒に実施していくような仕事です。
その過程で、地元の人たちの高い潜在能力に驚かされました。コミュニティのことをよく考えて、素晴らしいアイディアを考えつく人たちがいて、教育の機会さえあればどれほど仕事ができただろうと思うような人にたくさん出会いました。彼らがその能力をいかして活躍できるような社会になればいい。そのための力になるような仕事をしたいと強く思いました。
――なるほど。では、次はそれに直結する仕事を?
千葉:いいえ。カメラマンの夫にブラジルで仕事のオファーがあり、一緒に行くことにしました。子育てをしながら、遠隔でコンサルティングの仕事をしたり、ブラジルのテレビドラマに登場する日系人役の所作指導をしたり、仕事は続けましたが、もっとフルに仕事をしたい気持ちが募りました。
そして2017年、夫と共にケニアに戻ったのですが、6年のブランクができていたので、仕事をすることに対して少し自信を失っていました。
そんな時、出張でケニアに来ていたピースウィンズのマネージャーと出会って、現在のポジションにつながりました。
コミュニティを巻き込んでいく

――隣接するソマリア、南スーダンなどからケニアに流れ込む難民や亡命申請者は70万人を超えるとされます。巨大な難民キャンプにはさまざまな支援ニーズがある中で、ピースウィンズは現在、主に給水や衛生分野での支援を行っています。苦労も多いと推察しますが、どんなことにやりがいや喜びを感じますか?
千葉:難民キャンプには母国での対立関係が持ち込まれたり、世界の国々が人道支援に割く予算を大幅に減らすために事業を縮小せざるを得ないなど、問題は山積しています。特にケニアの難民キャンプは30年以上前から続くものもあり、これだけ長くなると、そこで暮らす人は援助に頼ることに慣れてしまって受け身になるなど本当に難しい問題はあります。
でも、コミュニティを巻き込んで働きかけを続ければ、時間はかかっても結果はついてきます。私にはその間の試行錯誤がおもしろい。たとえば、取り組んできた課題のひとつが衛生です。
従来の人道支援は「難民5世帯あたりトイレをひとつ」といった基準に沿ってトイレを作ってきましたが、誰も責任を持って管理しなければあっという間に汚くなって、誰もトイレを使わず、屋外排泄の習慣に戻ってしまう。排泄物が放置されると雨季にコレラが流行するなど命にも関わります。これでは埒があかない。やり方を変えなければダメだと思いました。

そこで、トイレを建てるだけでなく、コミュニティの一員でもある衛生啓発員を中心に、住民の人たちみんなで村の衛生の状況、何に困っているかなどを考え、自分たち自身でトイレを作り、気持ちよく使えるよう清潔に維持して使ってもらうようにしました。
最初は「トイレを作ってくれないなら支援の意味がない」といった冷ややかな態度だった人たちも、トイレがきれいになって屋外排泄がなくなると悪臭もなくなって「外で食べるご飯が美味しい」と言うようになりました。このほうが良いと納得してもらえると行動も変化します。粘り強い啓発の結果、2020年には政府のモニタリングで「屋外排泄ゼロ」と認定されてお祝いをしました(ただ、そのあとでまた新たな難民の流入があると揺り戻しはあります)。

――変化が見えると励みになりますね。
千葉:はい。他に、喜びを感じるのは、役所やコミュニティや国連、いろんなところに直談判や根回しに行って、相手の理解が得られ、それが結果としてプロジェクトとその成果に繋がったときにすごくうれしい。「やった!」という気持ちになります。
それが好きでこの仕事をしているんだろうなと思うこともあります。いったん理解して納得してもらえると、みんな献身的に動いてくれます。特に給水のようなライフラインの仕事をしているスタッフは、その大切さがわかっているので緊急事態には夜だろうが週末だろうが仕事をしてくれます。そういうスタッフと働ける喜びもあります。
――千葉さんが仕事をしていく上で心がけているのは、どんなことですか?
千葉:私は人にとっての尊厳は、自分が生きているという実感だと思っています。誰もが尊厳を保ち、生きがいをもって生きていく、それを後押しするための事業を進めるのが私の目標です。
1964年イギリスから独立。初代大統領ケニヤッタ時代(~1978年)経済成長を遂げ東アフリカ屈指の経済国となった。たが、その後クーデターなどで国内が混乱。2007年の大統領選挙のあと与野党の衝突が暴動につながり数多くの国内避難民を生んだ。国連事務総長による調停を経て2010年、新憲法が成立した。ケニアにはソマリア、南スーダン、コンゴ民主主義共和国などからの難民が流入し、UNHCRによると約100万人の難民・亡命申請者がケニアの難民キャンプで暮らしている。最大のダダーブキャンプには38万人以上が暮らしている。
千葉 暁子(ちば あきこ)
大学(社会人類学専攻)を卒業後、企業でマーケティングの仕事をした後、JICA青年海外協力隊員としてエジプトやヨルダンで仕事。東京都立大学大学院より修士号取得。2006年から2011年JICA調整員や専門家としてケニアに駐在。ブラジルでの生活を経て2017年にケニアに戻り、2018年からピースウィンズ職員としてナイロビに駐在する。