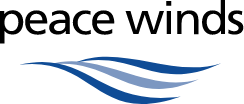ロサンゼルス山火事から4ヵ月――なお続く困難と、地域に根差した支援
2025年1月7日に発生したロサンゼルスの大規模山火事から、すでに4ヵ月以上が経過しました。しかし、被災地ではいまなお、多くの人々が困難な暮らしを強いられています。ピースウィンズの提携団体パサデナ・コミュニティ・ジョブセンター(PCJC)は、火災直後から被災者支援を行っており、現在も活動を継続しています。

発災当初は毎日実施していた食料や生活用品の配給は、いまは週1回となりましたが、配給日には、多くの人がセンターにやってきます。この日はセンターに隣接する広い倉庫兼駐車場を活用した物資配給ポイントができており、多くのボランティアの準備で順調に進んでいました。徒歩の列と車両の列が分けてあり、物資は企業や行政などから提供を受けています。配付されたのは、バゲット、卵、缶詰、飲料水などの食料に加え、おむつ、粉ミルク、衣類といった生活必需品。野菜や果物といったものも世帯ごとに持ち帰ることができるよう、箱に分けてありました。列にならんでいる人は、ラテンアメリカ系をはじめ、中国語を話す人やベトナム人、そして移民ではない地元住民の姿も見られます。ラテンアメリカ系の人が食べるもの、アジア系の人が食べるものといった文化的配慮もあり、必要なもののみ受け取って、自身がいらないと思うものは受け取らないというようなルールも徹底されていました。
この日の朝10時から始まった配給には、徒歩で物資を受け取りにきた人が約90人、車で来た人が50〜60台と、多くの人々がまだ支援を求めて列を作りました。物資を受け取にきた人について、最近どこから来たのか、どのような被害があったかなどをセンターの職員が聞くようになりました。とはいえ、さまざまな事情がある人たちでもあるので、基本的に誰でも受け入れて、支援を提供しています。

見えづらい困窮と直面する課題「誰も取り残さない」支援を
今回の火災によって多くの住宅が焼失しました。公費による焼失家屋の解体が進められていますが、3か月以上経ってもまだ2割程度の解体率で、静かな住宅街だった街には、焼けたままの住宅が多く残されています。とくに移民など公的な支援を受けにくい人にとって、住宅の再建は難しく、自力での生活再建は極めて困難です。公費解体の前に、瓦礫をきれいに撤去するだけでも1年半かかると言われます。

PCJC代表のパブロ・アルバラード氏は、「すべての人が尊厳を持って支援を受けられる場をつくりたい」と語ります。PCJCでは、日雇い労働者のための支援や仕事のマッチングを20年以上やってきていますが、火災後は仕事がずいぶんかわって日雇いの仕事はがれき撤去が中心になってきているそうです。ただし、これらのがれきのなかには、ガラスや釘などの危険物や、古い家屋のアスベストなど化学物質が残っているなど、多くの課題がありました。そこでPCJCは、日雇い労働者に瓦礫撤去の技術研修や安全研修を実施。彼らは「ブリガーダ・デ・セルビシオ(サービス隊)」として、焼け跡の清掃や被災家屋の片づけに従事しています。これまでに2,200トン以上の瓦礫を撤去し、地域社会に大きな貢献を果たしています。日雇い労働者の中には、自身や家族の住む場所がなくなっている人も多いのが現状です。被災し、仕事を失った人々が「支援する側」として立ち上がるこの取り組みは、地域社会の再生に希望をもたらすものであり、自尊心と新たなつながりを生む場ともなっています。
支援を受けづらい立場にある人々にとって、この支援は「最後のセーフティーネット」です。ロサンゼルスの復興は、まだ道半ば。ピースウィンズは、PCJCなどの提携団体と共にこれからも支援を続けていきます。