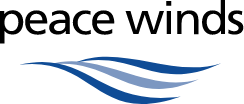世界の“水問題”とは? 3月22日「世界水の日」に考える現状と課題

3月22日は「世界水の日」です。日本では比較的水が豊富にあるため、その重要性を忘れがちですが、水資源には限りがあり、世界中でその管理と保護が求められています。この記事では、世界ではどのような水の問題が起きているのか、その実態や原因、国内外の対策について取り上げます。「世界水の日」を契機に水問題に対する理解を深め、現状を把握し、個人としてできることも一緒に考えていきましょう。
世界水の日とは?

「世界水の日(World Water Day)」は、私たちが水の大切さを見直し、持続可能な水資源の管理について考えるための日として、1992年に国連総会で制定されました。翌年の1993年から毎年世界中でさまざまなイベントやキャンペーンが実施され、2018年からは『水の国際行動の10年』がスタート。安全な水の確保や持続可能な水資源の管理を強化するための取り組みが世界的に進められています。

「世界水の日」が生まれた背景にあるのが、世界的な水不足への危機感です。地球は「水の惑星」と呼ばれますが、実際に人が飲んだり生活に使ったりできる淡水はごくわずか。人口の増加や経済活動の拡大により、多くの国で安全な水を確保するのが難しくなってきています。この深刻な課題に対処するため、国際的な意識を高め、各国が協力して解決策を考えることが不可欠です。

また「世界水の日」は、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の一環として、水問題を2030年までに解決するための行動を促す日でもあります。各国の政策だけではなく、私たち一人ひとりが水の使い方を見直し、未来に向けて大切に守っていくことも求められているのです。
世界における水問題の現状
地球の表面の約70%は水で覆われていますが、その大部分は海水であり、人間が利用できる淡水はわずか2.5%です。さらに、その多くは氷河や地下水として存在し、実際に使える水は全体の約0.01%といわれています。地球上のすべての水を浴槽1杯(約200L)にたとえると、人間が使えるのはスプーン1杯(約20mL)程度しかありません(*1)。
日本では、蛇口をひねれば安全な水が手に入りますが、世界では水不足が深刻です。地球規模で直面している水資源の課題について詳しくみていきましょう。
*1)国土交通省|世界の水資源
4人に1人が安全な水を利用できない
WHO世界保健機関の2023年度年次報告書によると、世界では35億人が安全な衛生設備を欠き、23億人が基本的な手洗い習慣を持っていないとされています(*2)。

特に発展途上国では、水道設備が不十分です。日本では、当たり前に手に入る安全な水ですが、ユニセフの調査によると2022年時点で世界では22億人が安全に管理された飲み水を利用することができず、そのうち2億9,600万人が改善されていない水を利用し、1億1,500万人は未処理の湖や川、用水路などの地表水に頼っています(*3)。
その結果、汚染された水を原因とする感染症が多発し、特に乳幼児の健康に与える影響は大きな問題となっています。ユニセフによると、水が原因の下痢性疾患により毎年30万人の乳幼児が死亡しており、これは1日あたり約800人に相当します。生命を守るうえで欠かせない課題なのです。

自宅にあり、必要な時に入手でき、排泄物や化学物質によって汚染されていない、改善された水源から得られる飲み水。
●基本的な飲み水(供給サービス)(Basic):
自宅から往復30分以内(待ち時間も含めて)で水を汲んでくることができる、改善された水源から得られる飲み水。
●限定的な飲み水(供給サービス)(Limited):
自宅から往復30分よりも長い時間(待ち時間も含めて)をかけて水を汲んでくることができる、改善された水源から得られる飲み水。
●改善された水源(Improved):
外部からの汚染、特に人や動物の排泄物から十分に保護される構造を備えている水源。例えば、水道、管井戸、保護された掘削井戸、保護された泉、あるいは、雨水や梱包されて配達される水など。
●改善されていない水源(Unimproved):
外部からの汚染、特に人や動物の排泄物から十分に保護される構造を備えていない水源。例えば、保護されていない井戸、保護されていない泉、地表水など。
●地表水(Surface water):
川、ダム、湖、池、小川、運河、灌漑用運河といった水源から直接得られる水
出典:ユニセフ|ユニセフの主な活動分野|水と衛生
*2)日本WHO協会|WHO 世界の水 ・ トイレ ・ 衛生設備 (WASH) 、2023年度年次報告書
*3)ユニセフ|ユニセフの主な活動分野|水と衛生
水不足が深刻化
国連の報告によると、2030年までに約7億人が生活や生産活動に必要な水が確保できない水不足の影響で、移住を強いられる可能性があります。
特にアフリカや中東などの乾燥地域では、降水量が少なく、水源が限られている点が大きな課題です。加えて人口増加や経済発展に伴い、農業や工業での水需要が急増し、水資源の枯渇が深刻化しています。

水不足の課題を考えるうえで、水資源の偏在化も重要な視点です。カナダのように水が豊富な国がある一方で、中東諸国では極端に少なく、国内でも都市部と農村部で格差が見られます。特に水の確保が困難な地域では、人びとが長時間かけて水を汲みに行かざるを得ず、それが教育や労働の機会損失につながり、また別の深刻な問題にもつながっています。
日本が抱える「水問題」
日本のような水が豊富な国でも、食料輸入を通じて「バーチャルウォーター(仮想水)」に依存しています。バーチャルウォーターは「輸入食料を国内で生産する際に必要となる水の量」です。
たとえば、トウモロコシ1kgの生産には1,800ℓの水が使われ、牛は大量の穀物を消費して育つため、牛肉1kgには約3,600万ℓもの水が必要です(*4)。日本の食料自給率は低く、令和2年度のカロリーベース自給率はわずか38%。つまり、日本は食料の輸入を通じて、間接的に海外の水資源を利用しているのです。
*4)環境省|バーチャルウォーター
世界の水問題の主な原因
世界の水問題は単なる資源不足の問題に留まらず、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、気候変動や人口増加、経済発展など、複数の原因について掘り下げていきます。
気候変動の影響による水資源の減少

地球温暖化により気温が上昇すると降雪が減少し、雪解けが早まることで春や夏の水資源が減少します。さらに、乾燥地域では降水量が減る一方、湿潤地域では豪雨が増え、洪水のリスクが高まっています。
実際に、2022年にはヨーロッパで深刻な干ばつが発生し、パキスタンでは国土の3分の1が水没する洪水が起こりました。国連防災機関(UNDRR)によると、過去20年で干ばつは約1.3倍、洪水は約2.3倍に増加したという報告もあります。気候変動の影響で降水の偏りが進み、自然災害の被害も増加傾向にあるのです(*5)。
特に発展途上国では、農業や生活用水の確保が困難で水不足が深刻です。気候変動がこのまま進行してしまうと、今後も水資源の安定性が損なわれる可能性が高く、持続可能な水の管理と国際的な協力が欠かせません。
*5)NHK|なぜ?世界で深刻化する水不足
人口増加と水需要の増加
国連が発表した『世界人口推計2024年度版』によると、2050年には世界人口がおよそ97億人、2061年には100億人に達し、水の需要も急増すると予測されています。特に途上国では人口増加と経済成長が水不足を一層深刻化させ、温暖化以上に大きな影響を与えるといった指摘もあります。

国連教育科学文化機関(UNESCO)によると、1950年から1995年にかけて世界の水使用量は約2.74倍に増加し、人口増加率(約2.25倍)を上回りました。特に生活用水の使用量は6.76倍に急増し、都市化や生活水準の向上が水需要をさらに拡大させています。
また、農業や畜産業の発展により灌漑水の使用が増えたことも水不足の要因です。水の供給と需要のバランスが崩れつつあるなか、持続可能な水の管理が世界的な課題となっています。
産業発展や生活スタイルの変化

産業の発展に伴い、特に製造業や発電所での水の使用量が急増し、水不足を加速させています。『OECD環境アウトルック2050』によると、2000年から2050年の間に、製造業の工業用水が400%、発電用水が140%、生活用水が30%増加し、全体で水の需要は55%増加すると予測されています。
また、都市化やライフスタイルの変化は、生活用水の消費を急増させる要因です。適切な排水処理がされない場合、工場や家庭の排水が河川を汚染し、水質の悪化や生態系の崩壊を引き起こすおそれがあります。
このように、産業発展と生活スタイルの変化は、水の需要とその質に大きな影響を与えているのです。
水を巡る国際的な緊張
水資源はしばしば国境を越え、共有された川や湖を巡る争いが生じています。たとえば、エチオピアの「グランド・エチオピア・ルネサンス・ダム」は、ナイル川流域のエジプトやスーダンとの対立を引き起こしました。そのほかにも、インダス川やヨルダン川など、世界各地で水を巡る国家間の対立が見られます。
今後、気候変動や過剰利用が水不足をさらに加速させ、農業の生産性低下や地域間・国同士の対立を引き起こすおそれがあります。水を巡る争いは、今後一層激化する可能性が高く、その解決には国際的な協力が不可欠です。
「世界水の日」に考える水問題解決への取り組み
日本では、水道水が飲めることが当たり前ですが、世界の多くの地域では安全な水が手に入らず、毎年多くの命が失われています。ここからは水資源の現状を知り、私たちにできることはなにか、水の問題の解決に向けた取り組みや個人でできる活動についてご紹介します。
国際機関やNGOの支援活動

国際機関やNGOは、水問題解決に向けたさまざまな取り組みをおこなっています。国連のSDGs目標6は、「すべての人々に水と衛生へのアクセスを確保する」ための指針です。たとえば、ユニセフは井戸や給水設備を設置し、教育を通じて衛生的な生活環境の提供を進めています。水は命の源と言われ、特に子どもたちの健全な成長に欠かせない安全な水の供給が重要です。
また、1981年に英国で設立された国際NGO「ウォーターエイド」は、40年以上にわたり水と衛生分野で活動を続けています。現在、世界30ヵ国以上で、地域に適した方法を取り入れたプロジェクトを展開しています。

ピースウィンズも、アフリカ・ケニアの難民キャンプをはじめ、世界各国で人道危機に直面する地域や人びとに対し、安全な水の供給に尽力しています。過酷な環境での安全な水を確保する私たちの給水支援を知ることでも、水資源の重要性を理解していただければ幸いです。
【関連記事】【ケニア】難民に安全な水を届けるための給水チームの奮闘
個人ができること
この世界的な水の問題に対し、私たち一人ひとりができることは多くあります。日常生活で水の節約を意識し、シャワーの時間を短縮したり、節水型トイレを利用したりすることなどもそのひとつです。また、支援団体への寄付やボランティア活動に参加することで、世界の水不足解決に貢献できます。
さらに、水資源の現状について学び、その知識を周囲に広めることも重要です。学校や職場、地域での対話を通じて、問題に対する意識を高める取り組みが広がれば、より多くの人びとが水問題の解決に向けて行動を起こすことが期待されます。

まとめ
水問題は、私たちの生活に深く関わる重要な課題です。その解決には現状や多様な要因を理解し、具体的な行動を起こす必要があります。「世界水の日」をきっかけに、水の大切さをあらためて考え、家族や周囲と水資源について話し合うことも大切です。日常生活で節水を心がけ、そして温暖化対策を視野に入れた実践は、未来の地球を守ることにつながるのです。
【参照】
国際連合広報センター|水の国際行動の10年 – 2018-2028 世界的な水危機を回避するために
国際連合広報センター|水と衛生に関するファクトシート
国際連合広報センター|歴史的な国連水会議、世界的な水危機と水の確保に対処する分岐点となり、閉幕
国連広報センター|世界の人口は今世紀中にピークを迎える、と国連が予測
ユニセフ|3月22日は「世界水の日」
ユニセフ|ユニセフの主な活動分野|水と衛生
ユニセフ|安全な水とトイレを世界中に
ユニセフ|WHO「水と衛生」最新報告書 安全な水と衛生の欠如がもたらす女性・女の子への不均衡な影響 初の詳細分析
環境省|Virtual water 世界の水が私たちの生活を支えています
国土交通省|世界の水資源
国土交通省|水資源の利用状況
国土交通省|水資源に関する世界の現状、日本の現状
日本水フォーマル|地球上の水問題
日本WHO協会|WHO 世界の水 ・ トイレ ・ 衛生設備 (WASH) 、2023年度年次報告書
地球環境研究センター|ココが知りたい地球温暖化
NHK|なぜ?世界で深刻化する水不足
NHK|「水がないと生きられない…」 資源の奪い合いは石油から水へ
ウェザーニュース|この20年で自然災害による影響はどう変化? 気候変動リスクで考えるべき「未来」
OECD日本政府代表部|OECD 環境アウトルック 2050:行動を起こさないことの代償SDGs globe|世界が抱える水問題とは?SDGs6の課題と解決策を徹底解説!